 |
5時55分 | 信濃大町駅前 この写真の右の車の脇が扇沢行きのバス乗り場 この時期の始発は6時15分。 扇沢には約40分で6時55分着である。 乗り場の前がチケット売り場である。料金は1330円。 (ピークシーズンは5時30分が始発) 駅の向こう側(駅の正面に立って右側にあるお土産売り場の裏が大きな市営駐車場場である。 因みに今回23日朝5時半に駐車して翌24日午後6時に出庫して3100円でした。 |
| 扇沢 この時期のトローリーバスの始発は7時30分。 とてもたくさんの登山者、観光客が並びます。 *JAFの割引は会員証だけでなくチケットが必要です。 |
7時15分 |  |
 |
7時44分 | 黒部ダム駅 約15分で黒部ダム駅に着く。 観光客は突き当りを左に曲がり改札をでるが、下の廊下には改札を出ずに直進して少し曲がった場所にあるカレ沢登山者出口から外部に出る。 |
| カレ谷沢出口 正面に立山の小山が聳えて見える。 ここで身支度とトイレを済ませて5分後に出発。 トンネルの出口にトイレがある。 ここを右下に下っていく。 詳細写真(1) 黒部渓谷下の廊下は黒部ダム建設に認可の付帯条件として関西電力に対して整備することが義務付けられており、毎年多額の費用をかけて整備されているという。 黒部ダムが観光に供されているのも付帯条件の一部なのだとか。 |
7時47分 |  |
 |
8時14分 | トンネル出口から約20分ほどで黒場ダムの下の河原に出て橋を渡る。 ここから黒部ダムが聳えて見える。 この時期観光用の放水が見られないのが残念。 |
| 黒部ダムから阿曽原温泉小屋まで約20㎞。そしてその先の欅平駅まで約30㎞ある。 これを2日かけて歩く。 阿曽原温泉小屋までが旧日電歩道。それから先が水平歩道と言われる。 この黒部渓谷の左岸の崖につけられた道を歩く(東谷吊橋から仙人ダムまでは右岸)。 朝日を浴びて紅葉が輝く。 詳細写真(2) |
8時45分 |  |
 |
8時56分 | 滝の上部に紅葉が。 このルートには沢山の滝を見ることができる。 ただ時として、ずぶ濡れになり渡渉に苦労する場所もある。 |
| 内蔵助谷 黒部ダム下の川を渡って歩き始めて最初の地図上のポイントである。 黒部三大岩壁丸山東壁 この沢の脇から、真砂岳への登山口がある。 |
9時7分 |  |
 |
9時25分 | 黒部峡谷の中でもとても狭い場所。 この辺りは河原のゴロゴロした大きな岩の上を乗り越えながら下る。 詳細写真(3) |
| 振り返ると背後に灌木が朝日に輝く。 この辺りはまだ崖を歩くという緊張感はない。 |
9時56分 |  |
 |
10時24分 | 次第に歩道の川からの高度が上がるが、それほどの恐怖心が生じるような高さではない。 しかし、「黒部では怪我はない・・」という言葉がある。怪我では済まないという意味。気を引き締めて歩道を進む。 |
 |
10時44分 | 新越沢出会 きれいな滝とコバルトブルーの瀞を見ることができる。 黒部ダムまで6.8km 仙人谷ダムまで9.8㎞ 欅平まで23.4km |
| そろそろ下の廊下が牙をむき始める。歩道の幅がとれない場所には丸太を組んでかけた桟橋の上を渡る。 濡れているときには滑りやすく注意が必要。 登山道には針金(番線)が付けられており、それを握りながら進む。 安全ロープや、ハーネスにスリングテープにカナビラを付けて番線にカラビナを掛ける準備をしている登山者もいたが(私達もそうでした)、カナビラを架ける時間はなく、番線を手で握り、足場に注意しながら進む以外にない。(ハーネスにスリングテープ、安全環付カラビナはイタリアのドロミテのビア フェラータ(VIA ferrata:鉄の道の意味)と呼ばれる岩場に固定されたワイヤーや鉄ハシゴの岩山縦走に使われるとこからフェラータセットとも呼ばれている。) 詳細写真(4) |
10時58分 |  |
 |
11時15分 | 振り返ると垂直な崖にを水平に穿かれた登山道が続く。 |
| この辺りに来ると残雪も多く、道が整備されていない場所は丸太を組んだハシゴを登り高巻く。 このハシゴはほぼ垂直に掛けられており、なかなか高度感もある。普通のハシゴと異なり直径10センチほどの丸太は握りにくく、滑りそうで勢い力が入る。テント泊の装備を背負っているため体が垂直になるとザックの重さ直接持ち上げる感覚があり、梯子を乗り継いで最上部に着く頃にはとても疲れた。 ベテランの登山者もとても怖くて疲れたと言っていた。しかし、ハシゴを登り終えて、この場所は高巻しなくてもいい場所であることに気づいた。 |
11時21分 |  |
 |
11時28分 | 上の写真のハシゴの高巻を降りた地点から振り返ると大きな雪の塊が見える。 |
 |
11時28分 | 歩道の幅がとても狭いため針金(番線)を頼りに慎重に進む。 |
| 黒部別山谷の出会い。 このルート上の2番目のポイントである。 見上げると白い岩の先の青空と紅葉が映える。 ここが大休止するための場所である。 この右側の急な崖をのぼて白竜峡へ向かう。 雪の多い年はこの沢は雪で埋まり雪渓の上を渡るらしい。 |
11時33分 |  |
 |
12時00分 |
赤ムケの壁と呼ばれる場所。 ここだけ岩が赤褐色で他と異なる。 高度感はないが足場が悪い場所を進む。 詳細写真(5) |
| 白竜峡の手前の2つ目のハシゴ。 これが見てのとおりとてつもなく大きなハシゴの高巻で、ほぼ垂直なハシゴ。ビルの4から5階ほどの高さ登る。そして水平につけられた丸太の桟橋を移動してまた下るのであるがとても緊張する。 この二日のうちで一番緊張し、恐かった場所である。 |
12時27分 |  |
 |
12時34分 | 白竜峡あたり ここがこのルートの地図上のポイント。 ここに白竜峡と書かれたプレートがある。 黒部ダムまで9.3km 仙人谷ダムまで7.3㎞ 欅平まで20.9km |
| 広河原と呼ばれる辺りは、青空も開けてしばらく緊張感から解放される。 | 12時44分 |  |
 |
12時58分 | 高度もますます下の廊下らしく高くなってきた。 遥か下の黒部川が見える。 詳細写真(6) |
| ここだけはどうしても多少は濡れてしまう。 それでもズタ袋をカーテンのようにして濡れるのを軽減してくれていいるが、それでも濡れました。 ここでカメラのレンズを濡らしてしまった。 |
13時25分 |  |
 |
13時37分 | ここが黒部川の秘境「十字峡」 右側が黒部川の上流(黒部ダム)で左側が下流。 向かい側の澤が棒小屋沢、そして手前側の沢が剣沢。 よくこのような見事な十字の渓谷ができるとは自然の神秘である。 ここが欅平までの中間点。 黒部ダムまで11.8km 仙人谷ダムまで4.8㎞ 欅平まで18.4km |
| 壁の上から沢山の錆びたワイヤーがぶら下がっている場所。とても高度感がある。 | 14時24分 |  |
 |
14時41分 | 半月峡の川底は良く見えなかった。 黒部の下の廊下らしい場所であるが、よくぞこの高さで、ここまで穿ったものである。 黒部ダムまで13.5km 仙人谷ダムまで2.7㎞ 欅平まで16.3km 詳細写真(7) |
| S字峡 確かに狭い峡谷がS字にくねって流れている。 半月峡とS字峡はよく判別がつかなかった。 |
15時05 |  |
 |
15時29分 | とても長い東谷吊橋 このとり橋は原則として一人ずつと書かれており、とても怖い。しかし中央あたり見るコバルトブルーの川の流れが見事。 東谷は五竜岳と鹿島槍ヶ岳を源流としている。 黒部ダムまで15.6km 仙人谷ダムまで1.0㎞ 欅平まで14.6km |
東谷の向かいの二つの建造物は黒部第4発電所のの送電線が外部に出る場所。 この山の地下に東京ドーム2個分ともいわれる巨大な黒四ダムの施設がある。 それにここにある車にはナンバープレートが付いていなかった。この黒部のトンネルの中と管理用の道路だけを走るためだという。 ダムのそばにいた関係者に、「あそこからサンダーバード2号が出てくるんですか。」と聞いたら笑いながら「そうですよ」と答えてくれた。 ありがとうございました。 「黒部ダム15.6㌔・欅平14.6㌔地点」と書かれていた。 |
15時36分 |  |
 |
15時49分 | 仙人谷ダム ダムの上を渡り管理事務所のある施設に入り、通路を利用させてもらって関電人見宿舎に向かう。 詳細写真(8) |
| 関電仙人ダムの管理施設 途中に高熱隧道のトロッコ列車のトンネル線路を越えて行く。 トロッコのトンネルを掘るにあたっての苦労については吉村昭著「高熱隧道」に詳しい。 このルートを歩くにあたってはぜひ読んでおきたい一冊である。 この本を読んでおくと仙人谷ダムから阿曽原、志合谷、欅平までの歩きが一味深いものになることは間違いない。 |
15時55分 |  |
 |
16時11分 | 関電人見宿舎の建物を越えると20分程とても急な登り返しがある。これがかなり厳しい。 詳細写真(9) |
| 阿曽原温泉小屋テント場(小屋の下にある) 小屋のすぐ下にテント場があり、私たちのテント場から5分ほど下に露天風呂がある(着替える場所もなくスノコが置いているだけです。)。 1時間交代で男女の入浴時間が入れ替わる。10月の後半にもかかわらずこのテント場はとても暖かく温泉に入った後、テントの前で冷たいビールと食事を楽しむことができました。 この日の夕食は巣鴨古奈屋のクリーミーなカレーうどんでした。とても美味しいうどんでしたが、重たい生めんを担いでくるのは大変でした。正面の建物が水洗のトイレと左わきが水場。 この日はとても混んでいて手前の私たちのテントは男女3名の若者のパーティーの勧めで彼らの脇の通路に立てさせてもらった。 温泉の写真は人が多いため撮れませんでした。 しかしとてもいい露天風呂でした。 |
17時14分 |  |
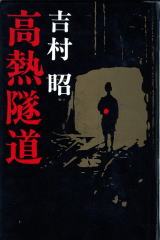 日本電力(現関西電力)黒部川第三発電所水路トンネル、欅平駅~軌道トンネル(現:関西電力黒部専用鉄道)の工事現場や人間関係について、建設会社の現場土木技師の目を通じて描いた作品。
日本電力(現関西電力)黒部川第三発電所水路トンネル、欅平駅~軌道トンネル(現:関西電力黒部専用鉄道)の工事現場や人間関係について、建設会社の現場土木技師の目を通じて描いた作品。