 |
7時41分 |
林道ゲート入口
東照宮脇から約3.6km程。
これら約2時間つづら折りの林道を登り高度を稼ぐ。
ひたすら林道歩きです。
(標高935m辺り)
|
稲荷川展望台からの展望
日向砂防ダム
総工費43億6千面をかけて昭和49年10月に着工し昭和57年9月に完成した。
日光の町と国宝を守るための砂防ダム。
日本一の砂防ダムの威容を誇る。
(標高1160m辺り)
左側が女峰山(2464m)、右が赤薙山(2010m)
両山のコルの下がアカナ沢(大鹿落とし) |
8時28分 |
 |
 |
9時3分 |
洞門岩の分岐
(標高1227m辺り)
ここから右に下ると沢ルート
林道を直進するルートは少し長いが一応安全なルートとのことにする。
林道は約30分ほど登ると最高点になる。
ここから雲竜渓谷入口となる展望台まで約40分。
沢ルートは雪の深いときはルートファンディングに苦労すつとのこと。そこで下山に利用することにした。 |
林道から分岐点
林道の最高点(標高m1360m程)を過ぎて少し下ると直進する林道から右に折れて下る道になる。
正面の山に凍りついた大きな滝が見える。
|
9時43分 |
 |
雲竜渓谷入口望むする堰堤の展望台
(標高1330m程)
正面の谷間が「友不知」(友知らず)と呼ばれる雲竜峡谷の入り口
ここが沢ルートとの合流点 |
9時52分 |
 |
 |
10時04分 |
急な階段を下り沢を渡渉するて。
これから雲竜瀑までの間に4カ所ほど凍てついた沢を渡渉するので注意が必要。 |
雲竜渓谷の入り口 「友不知」と呼ばれるいる凍てついたゴルジュ。
神聖な場所に入る氷の門のようである。
|
10時12分 |
 |
 |
10時19分 |
何回か沢を渡渉する。
凍りついた岩場を渡るにはアイゼンのグリップ力を信用してバランスよく岩に乗ること。
アイゼンに慣れていないハイカーは渡れずに困っている人がいました。
場所によってはアイスブリッジもあったが踏み抜きそうでできるだけ避けたほうがよさそう。 |
「友不知」と呼ばれる凍りついた狭いゴルジュが氷の神殿雲竜渓谷の入り口
日がよく当たる場所であるため溶けて崩落する危険な場世でもある。 |
10時20分友知らず |
 |
 |
10時20分
友知らず |
 |
 |
10時24分 |
「友不知」(友知らず)を抜けると燕岩と呼ばれる大きくハングした岩場に凍りついたつららと氷柱、氷壁きが続くエリアに入る。
氷の壁にアイスクライミングをしている。
ここに入るにはヘルメットがあった方がいい。 |
「友知らず」を振り返ると狭い谷間の奥に青空が見え、左岸の氷壁が輝いて見える。
氷の神殿の入り口は見事な渓谷美である。
左岸の氷の狭い歩道をアイゼンを利かせて歩いてくる。
しかし日差しを受ける場所であるため、融けて崩落するととても怖い場所でもある。 |
10時24分 |
 |
 |
10時27分 |
氷柱群が見事に育ったエリア。
しかし、気温の上昇のため崩れ落ちた氷柱もありこの下の入るのには緊張した。 |
 |
| 20m程の氷柱の裏側に入る。右奥に雲竜瀑が見える。山と渓谷「2011年2月号」の表紙はこの場所であった。10時28分 |
 |
13時34分 |
巨大なつららと氷柱
左手前には乗用車程の大きな氷柱が折れて落ちていた。
以前は「2月10日を過ぎたら雲竜に入るな」といわれたらしい。
それに気温が高くなると氷が解け落ちるために氷の締まっている寒い午前中の方がいいようである。 |
氷柱群を上部から望む。
このあたりの沢が広く沢山のトレッカーが食事をしたり展望を楽しむ場所になている。 |
10時36分 |
 |
 |
10時38分 |
上部にある雲竜瀑へは右の斜面を50m程登りそして高度間のある巻道を通過して滝下の広場に到達できる。
(標高1400m程)
ここは上部はしっかりしたアイゼンと登山技術が必要。
この斜面を登ることを躊躇して雲竜瀑(滝)まで行くことをあきらめるグループも多い。
上部の滝と下の滝が繋がって見えるがこれはカメラングルの関係でこのように見えるが手前の5m程の滝(F1)はアイスクライミングの装備がないと乗り越えられない。 |
最初から急なのぼりが始まる。高度がドンドン上がり、すべりやすい斜面のため気が抜けない。
この高巻道が雲竜瀑ルートにおける一番の難所。
軽アイゼンでは厳しいためあきらめるグループもかなりいた。
冬山の登山技術の無い人は無理しないほうがいい。 |
10時41分 |
 |
 |
10時46分 |
この急斜面の最上部の巻道はとても狭い。
標高差50m以上もあり足元に河原が見えるため高度感を感じる場所である。
アイゼンをしっかりと利かせればとくに恐怖心はない。 |
雲竜瀑(滝)の全景
落差160m
標高1550m程
高度感のある狭い巻道をトラバースすると眼前に真っ直ぐな氷結した雲竜瀑が現れる。
ここから雲竜瀑が上から一直線に落ちている様子が展望できる。
|
10時48分 |
 |
 |
10時49分 |
雲竜瀑の滝つぼの広場。
アイスクライミングのパーティーが取りついている。 |

上の写真は雲竜瀑の右の壁
アイスクライミングを楽しむクライマーたちが沢山いた。
雲竜瀑の下部
とても大きな滝のため全景を撮ることは難しと思われたが、一枚に収まった。
ここで暖かい日差しの下、ラーメンを作り雲竜瀑とアイスクライミングの様子を1時間ほどゆっくりと楽しんだ。 |
11時27分 |
 |
 |
11時43分 |
このエリアの中で一番大きな氷柱は約20m程あるがそれを垂直に登るクライマーがいた。
上部の雲竜瀑のエリアでアイスクライミングを楽しんでいたメンバーたちもこの垂直なクライミングの困難性は十分、分かっているらしく、皆「すごい」と口にしていた。
何より、この高い崖の上にトップロープをセットしたメンバーがすごい。
あとでメンバーに聞いたら下の写真の氷壁を登って上に登り灌木等を支点にしてトップロープをセットしたらしい。
ただアイスアックスを打ち込みアイゼンをけりこむため氷の破片がバラバラ落ちてきて危険である。 |
| 友知らずのゴルジュ。 |
11時55分 |
 |
 |
12時14分 |
雲竜渓谷への入り口である展望台
沢山のトレッカーが休んでいる。
写真を撮っている地点の裏側から沢ルートに下る。 |
砂防ダムのある左岸に取りつく。
沢ルートではここからしばらく稲荷川の左岸に付けられた登山道をくだる。巻道はこの区間だけである。
沢の下りではここだけが危険な場所のようである。
アイゼンを付けないトレッカーが恐る恐る下ってきた。
。 |
12時22分 |
 |
 |
12時29分 |
左岸の登山道から広い河原に降りるとその先が洞門岩の分岐へすぐの場所に出る。 |
洞門岩前の分岐
沢から登ると林道に出る。
ここには関係者の車が入ってきている。 |
12時36分 |
 |
 |
13時45分 |
林道のゲートに到着。
沢ルートで展望エリアから1時間30分で下ってきた。 |
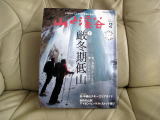 雲竜渓谷は世界遺産日光東照宮の脇の駐車場の間を抜けて3.5km程の林道ゲートから、約2時間ほど林道を歩くと到達できる。
雲竜渓谷は世界遺産日光東照宮の脇の駐車場の間を抜けて3.5km程の林道ゲートから、約2時間ほど林道を歩くと到達できる。





























